- 日本語
- English
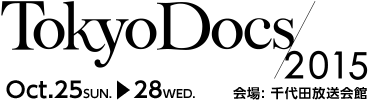
世界でのテレビ番組の国際共同製作は30年以上も前に始まっているが、日本での民間のテレビ番組製作会社や個人のドキュメンタリー制作者が国際共同製作に取り組む動きは2011年にTokyo Docsがスタートしてから本格的に動き出した(当初の2回はTokyo TV Forumの名称で開催)。Tokyo Docsは、2015年には5回目の開催となるが、国際共同製作のドキュメンタリーやテレビ番組の発信は着実に進んでいる。
こうした動きのきっかけは2011年3月にソウルで開かれたAsian Side of the Docというイベントだ。日本語同時通訳が用意されたため、東京からだけでなく大阪や北海道からもテレビ局、製作会社、広告会社、公共団体など映像制作にたずさわる関係者が多数参加した。
多くの参加者が最も興味を持ったのが、ドキュメンタリーの国際共同製作に向けた公開提案会議(ピッチング・セッション)だった。これはドキュメンタリーの制作者が自らの企画を直接、海外のテレビ局プロデューサーなど予算を持っている人たちに提案する企画会議だ。テレビ局プロデューサーの評価が得られれば、予算が提供されることとなる。日本のテレビ局との仕事がほとんどである日本の製作会社のプロデューサーにとっては、「世界への扉は開いていたのだ!」と肌で実感する機会となった。
海外でもドキュメンタリーは、映画やドラマなどに比べると決して主流のコンテンツではない。さらに、これまでドキュメンタリー製作を支えてきた公共テレビ放送は、経済状況の悪化や新しいデジタルメディアの台頭、そして若者のテレビ離れなどを受けて、従来のような潤沢な制作予算を提供できなくなってきている。もちろん日本でも状況は変わらない。
こうした厳しい状況の中、番組の製作予算を確保するために海外で盛んに行われているのが国際共同製作という仕組みだ。企画開発、製作資金の確保、撮影・編集などのさまざまな場面で複数の国のテレビ局やドキュメンタリー制作支援団体が協力し、共同で番組作りを進めるのが国際共同製作だ。
ドキュメンタリーの国際共同製作にはいくつかのタイプがある。
民間のドキュメンタリー制作者が、国際共同製作の形で製作資金を集めるのに広く使われているのがピッチング・セッションだ。Tokyo Docsでもこのピッチング・セッションがメインイベントとなっている。日本ではまだまだ広く知られるに至ってはいないが、海外では日増しに人気が高くなっている。特にアジアでは韓国やインドネシアなどでも、新しいピッチング・セッションが立ち上がっている。
そもそもピッチング・セッションとはどういった意味なのだろうか?“Pitch”を直訳すると「投げる」。ドキュメンタリーの世界では「提案を投げる」、つまり「提案をする」という意味で使われる。時に名詞的に「提案された企画」という意味にもなる。つまりピッチング・セッションとは「提案会議」だ。日本では2011年11月に、Tokyo Docs(当時は東京TVフォーラム)で初めてドキュメンタリーの国際的なピッチング・セッションが行われた。海外から招待された20人のディシジョン・メーカー(製作予算をもったテレビ局や財団のプロデューサー)に対し、21の企画が提案された。
ピッチング・セッションで好評を博しても、すぐに国際共同製作実現するわけではない。さまざまな資料を用意し、厳しい交渉を繰り返し、ドキュメンタリーの方向性について議論を重ねていく必要がある。ドキュメンタリーの国際共同制作が形になるまでには、長い道のりが待っているのだ。
しかしTokyo Docsから始まった国際共同製作は日増しに数を増やしている。海外のディシジョン・メーカーたちの日本の製作者に対する目線は、とても暖かい。Tokyo Docsでは、国際共同製作に対する理解を広めるため、年間を通してワークショップを開いている。また具体的に企画の実現に向けて動き出した場合には、さまざまなアドバイスも提供している。ピッチング・セッションを第一歩として、ひとりでも多くの日本のドキュメンタリー関係者が、世界に踏み出すことを願ってやまない。
Hot Docsは1993創設のカナダ・トロントで開かれる国際ドキュメンタリー祭。その名前はホットドッグ(hot dog)のスペルをもじったもので、“ホットなドキュメンタリー”という意味もあるようだ。毎年5月初旬に10日程度の日程で行われ、200本近くのドキュメンタリー映画が上映され20万人近い観客動員数を誇る。
同時に様々なIndustry programsが開かれる。ちなみにIndustryは直訳すると産業という意味。Industry programsもしくはIndustry eventsはドキュメンタリー産業を支援するために開かれるイベントだ。
IDFA(イドファ)はオランダ国内および世界のドキュメンタリー文化を活性化するために1988年に始まった。「ヨーロッパ最大のドキュメンタリー関連イベント」とされることに、業界関係者に異論は無い。
毎年6月後半に行われ、ヨーロッパのテレビ局、製作会社、配給会社を中心におよそ2000人が参加する。ピッチング・セッション、ワークショップ、テレビ局のプレゼンが行われるほか、参加団体がブースを出展したブースで、活発な意見交換、商談、国際共同製作に向けた話し合いが行われる。
会場は港沿いにあるイベント会場で、ドキュメンタリー祭としては珍しくテレビ局や大手プロダクションの展示も行われる。Hot Docs(カナダ)やIDFA(オランダ)と比べるとアットホームな雰囲気が感じられるイベントだ。
2014年が25回目の開催、毎年6月後半に行われている。2011年の実績報告によると参加者は1743人、コミッショニング・エディター(予算を持っているTV局や財団のプロデューサー)とバイヤーは290人、455団体が展示を行った。会場は港沿いにあるイベント会場で、ドキュメンタリー祭としては珍しくテレビ局や大手プロダクションの展示も行われる。Hot Docs(カナダ)やIDFA(オランダ)と比べるとアットホームな雰囲気が感じられるイベントだ。
イギリスのシェフィールドで5日間の日程で開かれるドキュメンタリー祭。これまではIDFAと競合する秋に開かれていた、2010年から6月に開催時期を変更した。IDFAとは日程が離れたが、こんどはフランス系のSunny Side of the Docと日程が近接した。TV局関係者の間でも「同じ6月に2回も出張できない。困った・・・」という声が聞かれる。 Rochelle)。大西洋をのぞむ、こぢんまりとした港町だ。
Sunny Side of the Docがアジアも含めた世界の企画が集まるのに対し、Sheffield Doc/Fest(シェフィールド・ドキュメンタリー祭)は、ヨーロッパを中心とした企画やドキュメンタリー関係者が集まる。特徴はピッチング・セッションが行われず、制作者とコミッショニング・エディターとのミーティングが集中的にオーガナイズされること。 Docs(カナダ)やIDFA(オランダ)と比べるとアットホームな雰囲気が感じられるイベントだ。
CNEXという台湾、中国、香港で活動しているドキュメンタリー支援団体が企画、運営するドキュメンタリー・イベント。Tokyo Docsの1年前の2010年に始まった。毎年9月に開かれる。主催者は「CCDFはドキュメンタリー制作の“場”(プラットフォーム)だ。つまりドキュメンタリー制作者を、デシジョンメーカー、配給会社、財団と結びつけ、ドキュメンタリー製作を支援し、プロフェッショナル達の交流を深め、国際共同製作を推進する」としている。
CCDFでは、制作者向けのワークショップ、トレーニングセッション、ピッチング・セッションなどが行われる。ピッチング・セッションで受け付けるのは“中国ネタ”に限られるが、日本から企画を応募することも可能だ。
2014年に本格的に始動した韓国のドキュメンタリー国際イベント。ピッチング・セッションに、ほぼ特化している。韓国の制作者向けのK Pitch、アジアの制作者向けのA Pitchなどが行われる。K Pitchの最優秀企画には約300万円が与えられるなど、資金的にもしっかりと制作者を支援する事でも知られている。
Sunny Side of the Docを開催するフランスの団体が2010年からアジアで開催しているドキュメンタリーのイベント。2010年は香港、2011年はソウル、2012年は東京、2013年はクアラルンプール、2014年は中国・成都、2015年は廈門(アモイ)で開かれた。これまではすべて3月の開催だ。
ASDでもワークショップやトレーニングセッションが行われるが、中心はピッチング・セッションだ。ヨーロッパを中心に北米、アジアのコミッショニング・エディターや財団関係者が参加する。
東京TVフォーラムという名称で2011年12月に第1回が開かれた、日本初の本格的なドキュメンタリーの国際イベント。2013年からTokyo Docs と名称を変更した。主催はNPO法人東京TVフォーラムと一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟(ATP)。総務省、経済産業省、国際交流基金、NHK、民間放送局、などの支援を受けている。
毎年、春と秋に行われる世界最大のテレビ番組マーケット。ドラマ、アニメ、ドキュメンタリー、ライフスタイル、リアリティ・ショー、フォーマットなど、あらゆるコンテンツが一同に会する。ドキュメンタリーの国際共同製作に向けたピッチや話し合いも行われるが、基本的にMIPTV/MIPCOMは“完成番組の市場”だ。
会場はフランス・カンヌのPalais des Festivals。カンヌ映画祭と同じ会場だ。広い会場に多くのブースが並ぶ。「これほどたくさんのテレビ局、配給業者、製作プロダクションが世界には存在するのだ」と圧倒される。バイヤー、セラーは30分単位で打合せをブッキングするが、会場が広いので、うまくスケジューリングしないと移動ばかりに時間をとられることになる。
Tokyo Docs では、ドキュメンタリーの製作資金調達の新しい可能性を切り拓くために、2013年からクラウドファンディングの運営会社である株式会社モーションギャラリーと提携を始めました。
クラウドファンディングとは、インターネットを通じて市民から幅広く資金を募るシステムで、欧米はもとより、最近日本でも映像作品をつくるための製作資金調達に活用されています。
モーションギャラリーのホームページより
クラウドファンディング(英語:crowd funding)とは、クリエイター・表現者が不特定多数の人からプロジェクト資金を募る事を指す、群衆(crowd)と資金調達(funding)を組み合わせた造語で、プロジェクトを始める前の段階でアイデアを元に資金を募る、新しい資金調達の仕組みです。
映画、アート、音楽、ゲーム、出版や、イベントの開催、そしてソーシャルグッドな活動など、様々なクリエィティブ活動をスタートさせる新しい形として活用されています。
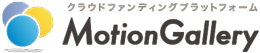
モーションギャラリーは、日本国内で最大級のクラウドファンディング・プラットフォームで、これまで映像作品の製作資金調達に関して、多くの実績を残しております。
Tokyo Docs第1回目(TTVF 2011)の参加企画である「ニュークリア・ネイション」は、劇場公開版の続編「フタバから遠く離れて[第二部]」の製作にあたってモーションギャラリーでクラウドファンディングを行ない製作費の一部の調達を行なっております。
またTokyo Docs 2013の参加企画である「フクシマ~放射能汚染の中であふれる『いのち』~」も、モーションギャラリーでクラウドファンディングを行ない「ナオトひとりっきり Alone in Fukushima」として劇場公開を実現しました。
さらにTokyo Docs 2012の参加企画である「警戒区域内の真実」は、劇場公開版「被ばく牛の生きる道」としての完成を目指し、2015年11月25日までのクラウドファンディングを現在行なっています。
そして今回のTokyo Docs 2015の参加企画である「2つのクジラの物語」は、既にモーションギャラリーで一部の資金調達を行なったうえでのTokyo Docs応募となります。
今回のTokyo Docs 2015のピッチングセッション参加企画で、これからクラウドファンディングを検討されるものについては、Tokyo Docs実行委員会からモーションギャラリーに公式推薦いたします。