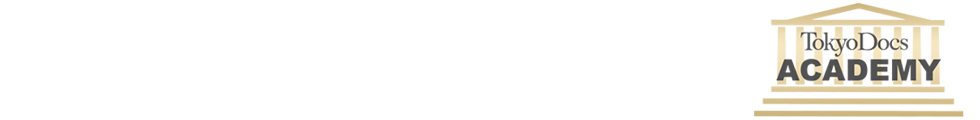Hot Docs 2014 参加報告
報告Tokyo Docs 実行委員/テレビマンユニオン 大野留美
Hot Docs北米最大のドキュメンタリーフェスティバル@トロント
- ■ 4月27日(日)~5月2日(金)に参加。
-
ほぼ全てのイベントへ入場可能な All-Access Pass を手配して頂いたので、初参加ながら Hot Docs 全体を自由に体験することが出来ました。
トロント大学の施設や、ドキュメンタリー専門劇場 Bloor Hot Docs Cinema など、徒歩圏内に大変恵まれた環境が整っていて羨ましい限り。運営スタッフには、毎年9月に開催さ れるトロント国際映画祭との兼任者も多く、映画祭運営の高い経験値を活かして、大勢のボランティアスタッフを潤滑に統率していました。
Hot Docs を構成するのは、
①企画ピッチングやミーティングが行われるインダストリー・イベントと、
②一般の観客に向けて各国のドキュメンタリー作品が上映される映画祭。
① インダストリー・イベント
Tokyo Docs から派遣された3名は到着翌朝の International Co-production Day ミーティングから活動開始。各自、今村さんのサポートを受けながら、事前にセッティングしてあ った相手とのミーティングを15分間隔で次々と行いました。探り探りの様子ながらも、国際イベントに参加している実感を早くも掴み始めているのが、見ていても分かりました。
Producer-to-Producer Meeting、Micro Meeting、Close Up with meeting などの合間に、連日開催される様々なワークショップやセミナーは、世界でドキュメンタリーを制作、発表、そしてビジネスとして展開していくうえで知っておくべき技術(撮影、編集機材など)からマーケットの状況(放送・配信形態の動向など)まで、参加者たちが幅広い情報を得られるように組まれていました。中でも個人的に興味深かったのは、映画祭でも特別上映されていた作品『The Sheik』の "hybrid distribution" について。80年代に人気を博したイラン出身プロレスラーで、現在もフォロワー数40万人を超えるツイッター等で人気の "アイアン・シーク" を追ったカナダ作品なのですが、SNS のファン層に直接リーチしやすい Vimeo での先行有料配信($10)を5月31日から始めて、その後に Super Channel での放送とシネコンでの上映を組むという、旧来の配給スキームから逆転した計画が面白かった。
二日間に渡る Hot Docs Forum(企画ピッチング)は今年で15回目の開催。(映画祭は今年で21回目。)128本の応募企画から選ばれた20本が提案されました。トレーラーを含めたピッチング7分 + デシジョンメーカー達の意見への対応7分と、与えられた時間が極め て短いにも関わらず、充実した情報量を分りやすく構成した堂々たるプレゼンテーションで、レベルの高さに圧倒されそうになりました。しかし、そんな彼らもやはり人の子。資 料を持つ手元を見ると震えている人も、原稿のパラグラフをごそっと飛ばして読んでしま ったことに後から気付く人もいました。彼らがそんな緊張の中でも Forum に挑み、チャン スを活かしているのですから、日本の制作者にも出来ないワケはありません。
Tokyo Docs の提案者に特に参考になりそうな点は、情報だけでなく作品のトーンも上手く伝えるトレーラー作りと、厳しい意見にも落ち着いて対話を続けられる客観的な視点を企 画にもつこと。協力を得られそうなデシジョンメーカーと事前にミーティングを済ませている段取りの良さも参考にすべき点でした。事前ミーティングで得たフィードバックを早速ピッチングに反映して、他のデシジョンメーカーからも前向きな反応を引き出すことに成功していたケースもありました。
休憩中に話した Shaw Media の男性から聞いた企画ピッチの基本的なチェックポイントは、 "great story"、"compelling characters"、"special access"、"production skill"、そして "good timing" とのこと。
提案された企画の中の1本『(Dis)Honest – The Truth About Love』をピッチングしたのは、昨年のアカデミー賞短編ドキュメンタリー部門を『Inocente』で受賞した Yael Melamede 監督。直接、話す機会があったのですが、数年前、企画段階だった『Inocente』でも Forum に参加していて、今回は2回目とのこと。今回のテーマである "嘘" を明るく捉え過ぎているのではないかというニック・フレイザー(BBC)の意見についても、「Forum に参加するのは制作費を集めるためだけでなく、制作途中に色々な立場のプロの生々しい反応を聞いて、完成前に作品を客観的にコントロールし直すチャンスを得るため」と余裕の構えでした。「自分が大切に思っている核心はぶれないけれど、観客の存在をすっかり忘れて入り込んではダメだから」「Forum で発表された企画は完成した段階で既に一定の注目が集まりやすい」とも。
多くのデシジョンメーカーの中でも、メッテ・ホフマン(DR)とニック・フレイザー(BBC)の存在感は、色々な意味で(笑)やはり別格でした。このようにレベルの高いピッチングを長年受けている方たちが Tokyo Docs に参加しているのだと思うと、改めて提案のレベルアップの必要性について考えさせられました。
バイヤーや映画祭のプログラマー向けのオンライン試写サービス Doc Shop では、予約制で利用できる約50台のモニターと、高画質動画の再生に十分対応できる回線を用意。配給会社の担当者たちもミーティングや Forum の合間に利用していて、会期後半には予約がいっぱいになっていました。
地元トロントのあるプロデューサーによると、参加者の大半が北米からで、年々ヨーロッパからの参加者は減っている印象だそうです。ただそれは、ヨーロッパは IDFA など幾つ かのドキュメンタリー映画祭が充実している上に、巨大な映画マーケットを併設するカンヌ国際映画祭のわずか 10 日前という開催時期のせいではないかとも思います。一方アジアは、まだまだ long way to go な状況・・・。
Producer-to-Producer Meeting、Micro Meeting、Close Up with meeting などの合間に、連日開催される様々なワークショップやセミナーは、世界でドキュメンタリーを制作、発表、そしてビジネスとして展開していくうえで知っておくべき技術(撮影、編集機材など)からマーケットの状況(放送・配信形態の動向など)まで、参加者たちが幅広い情報を得られるように組まれていました。中でも個人的に興味深かったのは、映画祭でも特別上映されていた作品『The Sheik』の "hybrid distribution" について。80年代に人気を博したイラン出身プロレスラーで、現在もフォロワー数40万人を超えるツイッター等で人気の "アイアン・シーク" を追ったカナダ作品なのですが、SNS のファン層に直接リーチしやすい Vimeo での先行有料配信($10)を5月31日から始めて、その後に Super Channel での放送とシネコンでの上映を組むという、旧来の配給スキームから逆転した計画が面白かった。
二日間に渡る Hot Docs Forum(企画ピッチング)は今年で15回目の開催。(映画祭は今年で21回目。)128本の応募企画から選ばれた20本が提案されました。トレーラーを含めたピッチング7分 + デシジョンメーカー達の意見への対応7分と、与えられた時間が極め て短いにも関わらず、充実した情報量を分りやすく構成した堂々たるプレゼンテーションで、レベルの高さに圧倒されそうになりました。しかし、そんな彼らもやはり人の子。資 料を持つ手元を見ると震えている人も、原稿のパラグラフをごそっと飛ばして読んでしま ったことに後から気付く人もいました。彼らがそんな緊張の中でも Forum に挑み、チャン スを活かしているのですから、日本の制作者にも出来ないワケはありません。
Tokyo Docs の提案者に特に参考になりそうな点は、情報だけでなく作品のトーンも上手く伝えるトレーラー作りと、厳しい意見にも落ち着いて対話を続けられる客観的な視点を企 画にもつこと。協力を得られそうなデシジョンメーカーと事前にミーティングを済ませている段取りの良さも参考にすべき点でした。事前ミーティングで得たフィードバックを早速ピッチングに反映して、他のデシジョンメーカーからも前向きな反応を引き出すことに成功していたケースもありました。
休憩中に話した Shaw Media の男性から聞いた企画ピッチの基本的なチェックポイントは、 "great story"、"compelling characters"、"special access"、"production skill"、そして "good timing" とのこと。
提案された企画の中の1本『(Dis)Honest – The Truth About Love』をピッチングしたのは、昨年のアカデミー賞短編ドキュメンタリー部門を『Inocente』で受賞した Yael Melamede 監督。直接、話す機会があったのですが、数年前、企画段階だった『Inocente』でも Forum に参加していて、今回は2回目とのこと。今回のテーマである "嘘" を明るく捉え過ぎているのではないかというニック・フレイザー(BBC)の意見についても、「Forum に参加するのは制作費を集めるためだけでなく、制作途中に色々な立場のプロの生々しい反応を聞いて、完成前に作品を客観的にコントロールし直すチャンスを得るため」と余裕の構えでした。「自分が大切に思っている核心はぶれないけれど、観客の存在をすっかり忘れて入り込んではダメだから」「Forum で発表された企画は完成した段階で既に一定の注目が集まりやすい」とも。
多くのデシジョンメーカーの中でも、メッテ・ホフマン(DR)とニック・フレイザー(BBC)の存在感は、色々な意味で(笑)やはり別格でした。このようにレベルの高いピッチングを長年受けている方たちが Tokyo Docs に参加しているのだと思うと、改めて提案のレベルアップの必要性について考えさせられました。
バイヤーや映画祭のプログラマー向けのオンライン試写サービス Doc Shop では、予約制で利用できる約50台のモニターと、高画質動画の再生に十分対応できる回線を用意。配給会社の担当者たちもミーティングや Forum の合間に利用していて、会期後半には予約がいっぱいになっていました。
地元トロントのあるプロデューサーによると、参加者の大半が北米からで、年々ヨーロッパからの参加者は減っている印象だそうです。ただそれは、ヨーロッパは IDFA など幾つ かのドキュメンタリー映画祭が充実している上に、巨大な映画マーケットを併設するカンヌ国際映画祭のわずか 10 日前という開催時期のせいではないかとも思います。一方アジアは、まだまだ long way to go な状況・・・。
② 映画祭 上映作品
数197本。
今年の動員観客数は 192,000 人を超えて、これまでの記録を更新したとのこと。
40か国以上から選ばれた上映作品を概括すると、いま世界の制作者たちが関心を寄せるテーマの傾向のようなものが見えてきて面白い。例えば、紛争が長引くシリアと、(プーチン大統領の反同性愛法案へのカウンター現象なのか)LGBT をテーマにした作品が多く見られました。
残念だったのは、日本作品の上映がゼロだったこと。プログラミング担当者の中に知り合いの Angie Driscoll と Myrocia Watamaniuk がいたので、日本の応募作品の印象を聞いてみました。「ボイスオーバーで自分語りや説明していく作風が多い印象。個人的なテーマで も全く問題ないけれど、そこにも背景にある時代や政治への意識がちゃんと感じられる作品をもっと観たかった」など、ローカルなテーマを大局的に捉えきっていない、内的に完結しているという印象を持った様子でした。日本の地方局などが制作している作品には、彼らが興味を持ちそうなものもありそうなので、今後は国際映画祭への応募を勧めてみることも必要なのかもしれません。
今年の動員観客数は 192,000 人を超えて、これまでの記録を更新したとのこと。
40か国以上から選ばれた上映作品を概括すると、いま世界の制作者たちが関心を寄せるテーマの傾向のようなものが見えてきて面白い。例えば、紛争が長引くシリアと、(プーチン大統領の反同性愛法案へのカウンター現象なのか)LGBT をテーマにした作品が多く見られました。
残念だったのは、日本作品の上映がゼロだったこと。プログラミング担当者の中に知り合いの Angie Driscoll と Myrocia Watamaniuk がいたので、日本の応募作品の印象を聞いてみました。「ボイスオーバーで自分語りや説明していく作風が多い印象。個人的なテーマで も全く問題ないけれど、そこにも背景にある時代や政治への意識がちゃんと感じられる作品をもっと観たかった」など、ローカルなテーマを大局的に捉えきっていない、内的に完結しているという印象を持った様子でした。日本の地方局などが制作している作品には、彼らが興味を持ちそうなものもありそうなので、今後は国際映画祭への応募を勧めてみることも必要なのかもしれません。
まとめ――
Tokyo Docs の第一の課題は、提案者/制作者の育成と企画の開発だと再確認しました。
そして、制作者と観客、両輪の相乗効果で発展してきた北米最大のドキュメンタリー・イベントに参加して、インダストリー・イベントの要素が主な Tokyo Docs も、ドキュメンタリーの観客層を広げていく上映会/映画祭を併せ持つ長期計画が、(現在の予算では相当難しいと思いますが)必要なのではないかと感じました。
そして、制作者と観客、両輪の相乗効果で発展してきた北米最大のドキュメンタリー・イベントに参加して、インダストリー・イベントの要素が主な Tokyo Docs も、ドキュメンタリーの観客層を広げていく上映会/映画祭を併せ持つ長期計画が、(現在の予算では相当難しいと思いますが)必要なのではないかと感じました。